 監督の言葉
監督の言葉
ニューヨーク在住の作家リリー・ブレットは、私の故郷であるバイエルン州の南ドイツから車で20分のところにある、フェルダフィングのDPキャンプで生まれました。そこは、アウシュヴィッツ=ビルケナウやダッハウの死の収容所から米軍によって避難させられたポーランドやハンガリーのユダヤ人たちが集められた場所であり、リリー・ブレットの両親がアウシュヴィッツの門で引き離された後、再会を果たした場所でもあります。私は16歳の誕生日に母からリリーの本を贈られ、初めて彼女の作品を読みました。母自身もリリーと同じくホロコーストの生存者の娘であり、リリーが作品に描くことで声を与えた“第二世代”でした。
リリー・ブレットの小説『Too Many
Men』を映画化した私たちの作品は、まったく異なる父と娘の“愛の物語”に焦点を当てています。ホロコーストの生存者であるエデク・ロスワックスは、力強く、楽観主義で、思いやりがあり、出会う人すべてと友達になります。しかし、彼の娘であり、私たちの物語の主人公であるルーシーは、両親のトラウマを抱え、家族が命を落とした地であるポーランドに対して怒りと苦々しさを抱いています。
このほろ苦い物語は、リリー・ブレットの小説の軽妙でユーモラスなトーンで語られていますが、登場人物たちが抱える深い痛みは隠すことなく描かれています。
映画の舞台は1991年。鉄のカーテンが崩壊した直後のポーランドが背景です。世界中、特にアメリカから多くのユダヤ人が東欧を訪れ、家族が遺したものを探る旅に出ました。ルーシーもその一人です。最初は父親の同行を煩わしく感じますが、旅を通じて彼女は父親を理解し、自己理解と世代を超えて受け継がれるトラウマへの洞察を深めていきます。
私は、レナ・ダナムとスティーヴン・フライがルーシーとエデク・ロスワックスを演じてくれることに大いに喜びを感じています。彼らは国際的なスターであるだけでなく、物語との個人的なつながりも深いのです。二人の家族はユダヤ系で、東欧にルーツを持っています。さらにスティーヴンは、ルーシーと同様の旅を実際に経験しています。そして二人とも、悲劇と喜劇を自然に融合させる一流の俳優なのです。
── ユリア・フォン・ハインツ
historical background歴史背景
第二次大戦後ソ連の強い影響下に置かれたポーランドは、いわゆる「鉄のカーテン」の東側、共産圏に組み込まれた。その後1989年のポーランド円卓会議と部分自由選挙によって、共産党政権が事実上崩壊。1991年、ポーランドでは初の完全な自由選挙が実施された。これにより旧共産主義勢力に代わる多くの新党が登場し、多党制民主主義が本格的にスタートした。経済的にも急進的な市場経済化が1990年に導入され、インフレや失業が急増、経済的困難に直面していたが民間経済は徐々に成長した。また、ワルシャワ条約機構(冷戦における旧東側の軍事同盟)からの脱退が進行中で、西側諸国との関係が強化され、欧州連合(EU)への加盟が視野に入り始めていた。※2004年に加盟
本作品の舞台である1991年という時代はポーランドという国にとって、政治的自由化と経済改革が同時進行する激動の時代で、新しい民主国家としての土台を築いていた時代であった。経済的不安が広がっており、格差や不満が増加し多くの人々が旧体制への郷愁と新体制への期待の間で揺れていたと言える。
またアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所は1979年に世界遺産に認定されており、1980~90年代は、冷戦の終結や国際的な教育の広がりにより、訪問者が増加した時代でもある。様々な理由から再訪が難しかったホロコーストの生存者たちも訪れるようになった。現在は生存者の高齢化が進み、第二世代・第三世代の来訪が中心となっている。










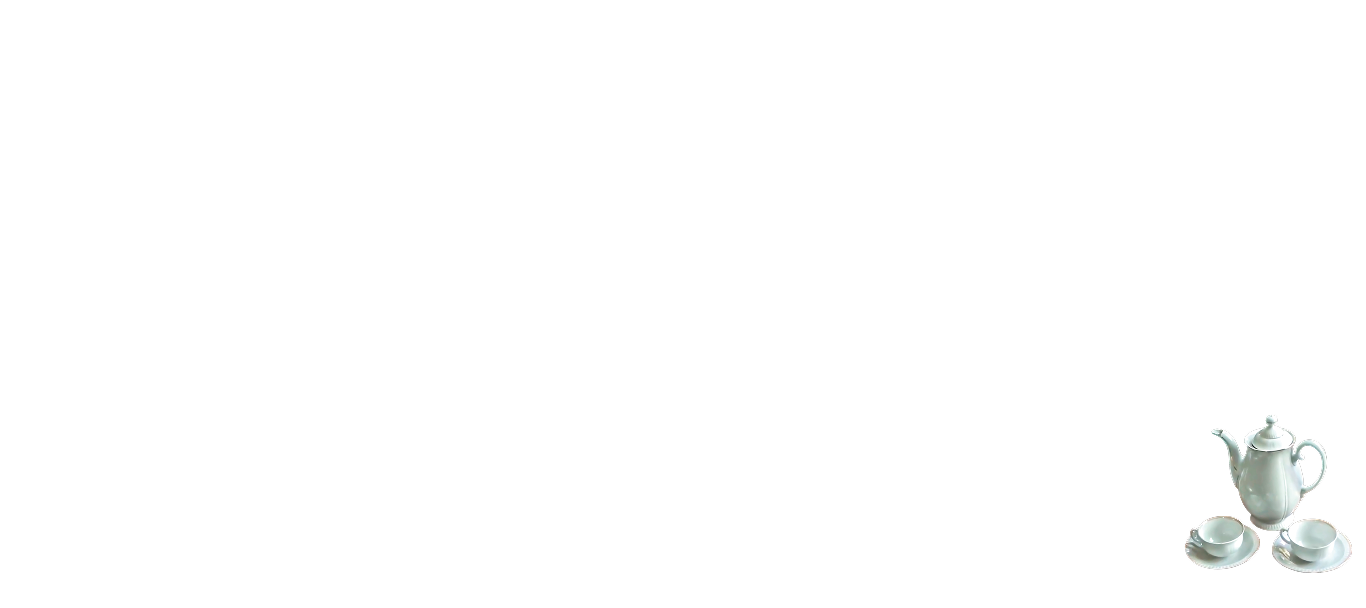


























順不同、敬称略
桃井かおり 女優・監督
時々忘れているが、我らの父母は、皆、壮大な歴史の中にいた。
軽やかに生きている父が抱えている歴史を、娘は十分大人になって、初めてその重さをまるで引き継ぐ様にありふれた日常から過去に、旅する。
愛おしいスティーブン・フライと、どの時代にあっても存在感を見せ付ける天使レナ・ダナムが連れて行ってくれた場所で、私たちも存在した。
この映画を楽しんだ、馬鹿笑いした、泣いた、身に染みた。
マライ・メントライン 文筆家
いま、まさに「あの」歴史的惨劇が、主客を変え形を変えながら繰り返される中、語られない家族のトラウマもまた、時代を超えて繰り返される。観客の想像力が重要なのだ。
佐々木俊尚 文筆家
陽気で楽しげで思いきり魅力的だけど、その奥底に辛すぎる過去を隠している父。NYで仕事に邁進してるのに心にわだかまりを抱いてる娘。そのふたりの思いのぶつかり合いに、笑って泣いて最後は本当にしみじみと感動した。明日からも頑張って生きよう。
森田聖美 フィガロジャポン本誌編集長
あまりに辛い経験をすると、人は直視できず記憶から遠ざけてしまおうとする、生き続けるために。でも、その深い悲しみへも敬意を持てる人間でありたい。本作の父娘の関係を見るとそう感じるのだ。
ISO ライター
「生き残れたから悲劇は終わり」ではない。ホロコーストという蛮行の波紋は時代を超え、新天地で生きる家族の絆や子どもの自尊心を静かに崩壊させる。過去と向き合い、それを取り戻すための再生の旅路は、切なくも優しく心に響く。親子を演じたレナ・ダナムとスティーブン・フライのケミストリーが実に素晴らしい。
風間晋 ジャーナリスト
「家族にも友だちにも本心は明かさない」
冷戦下の東欧では、誰もが心を固く閉ざした。
悲惨な記憶や日常の抑圧から身を守るためだ。
本作で描かれた自己解放と人々の関わり。
それが誰の人生でもみつかることを切に願う。
久山宏一 ポーランド文化研究
戦前ポーランドに居住していたユダヤ人が土地・建物の所有権を主張し、実際に訴訟に至ったという話は、噂話としては知っていたが、この映画が提示するのは驚くべき解決である。両民族の苦い共生史の中に、実際にこのような鮮やかな結末があったことを知り、ほっと安堵の息をついている。
武田真一 フリーアナウンサー
私の祖父はレイテ島で戦死した。何があったか聞くことはできなかった。歴史の継承の機会は貴重だ。それが痛みを伴うものであっても。この作品の父娘も歴史に傷つけられている。しかし、ふたりの泣き笑いの旅は、観る人の心を温めてもくれる。悲しみを抱きつつ、それでも生きるひとの強さを感じた。
山崎まどか コラムニスト
女優としてのレナ・ダナムの最高傑作。スティーヴン・フライと本物の親子みたいに見える!
辛い過去と懐かしい思い出が対になって次世代に手渡される瞬間、家族の歴史も変わっていくのだと感じました。
いとうあさこ お笑い芸人
家族はむずかしい。
家族だからこそ言えないこと。知りたいこと。見せたくないこと、見たくないこと。そして伝えるべきこと。父と娘のその姿は、めちゃくちゃ苦しくて、でもどこかコミカルで。笑いながら泣いてしまった。
劇場スタッフからも絶賛の声続々!
川添勇也 [サツゲキ]スタッフ
旅を終えた父娘を乗せた車が遠ざかっていく道。その傍らに立つ、錆び付いた看板の裏側がすごく印象的でした。“どうしても分かり合えない部分”の演出が素晴らしく、迫害当事者の父親にしか見えていない景色、聞こえない音があって、娘にもダイエットや離婚など当事者にしか分からない日常の問題がある。誰もがそうした裏側を持っている。後部座席で自分のあげた本を読む娘を見る、父親のあの暖かい眼差しが忘れられません。
戸村文彦 [塚口サンサン劇場] 番組編成担当
あの時代を生き抜いた父と、今を生きる娘。父の過去を巡る旅の中で明らかになるそれぞれの想いは、時に残酷で、時に優しく、不器用なふたりの心の距離がゆっくりと縮まる様子が、じんわりと心の奥にまで染み渡りました。戦争の傷跡は、形だけではなく記憶として残っていくものだと思わされました。だからこそ映画は、その記憶を物語として伝えていかなければならないし、それができるのが映画だと強く思いました。
大西彩 [豊岡劇場] スタッフ
全体的に穏やかな映画であるにも関わらず目が離せない。それは出てくる人々の根底に流れる悲しみと、それでも生きていくのだという強さがそこここに溢れているから。自分のルーツを、そして父の本心を知りたい娘と、娘を想いながらも軽口で本音を隠し続ける父。そんなふたりの気持ちはすれ違い続けているのに、互いを想い合う気持ちはずっと溢れている。1991年当時のポーランドという国の持つ暗さ、貧しさは衝撃的。ただ、出てくる人々の個性と温かさ、軽妙なセリフのおかげで陰鬱さをさほど感じさせず、後味の良い作品となっている。
合木こずえ [塩尻東座] 代表
父娘の距離感と心情の描き方が絶妙だ。愛情深い父親は、会話がなくても常に娘の動向を窺い性格を把握しているが、自らの過去は語りたがらない。娘はいつからかバリアを張り、父親の内側までは覗かなくなる。この関係は、いずこも同じか。娘の気持ちはストレイトに、父親の秘めた思いは滲み出るように伝わって胸をしめつける。演ずる二人の自然体が素晴らしい。いたましい悲劇の傷跡をユーモアと愛で包んだ演出力に喝采を送りたい。
U [静岡シネ・ギャラリー]
どんな旅でもそうですが、『旅の終わりのたからもの』というタイトルだからって、一足飛びに最終地点に直行すればお宝が手に入るものではないですよね。足並みの揃わない二人旅で、連れにイライラしたりガッカリしたり。そういう「できればない方がいい」旅の途中のあれこれがあってこその、旅の終わりのたからもの。映画だって、結論のためだけに観るのではないはず。映画館のくらやみの中に2時間座るのはむしろ、「できればない方がいい」途中のあれこれを効率悪いけれど大切に、身体に沁み込ませるため。だからド派手な大作よりも映画館で観てほしい映画です。そうすればたからものが見つかるはずだから。
木下裕一 [kino cinéma天神] 支配人
ポーランドの歴史を背景に、ふたりの旅はいつもちぐはぐ。いちいちイヤな言葉を選ぶ父に娘はうんざりで、、でも気にしてるからやめてあげてほしい笑 アウシュヴィッツ収容所の当時を想像させる広い空と父の記憶が、辛く心を締め付ける父娘は互いの《過去》と《現在》を確かめ合いながら、今を理解しあうのです。やっぱり家族旅はするべき!家族で映画旅もいいものです!
大野 匠 [kino cinéma新宿] 支配人
NYで育ち、自身のルーツを求めポーランドに来た娘と同行してきたマイペースな父親。 父娘らしいすれ違いの連続でユーモラスで騒がしい旅ですが、時折描かれるホロコーストを生き抜いた父のつらい記憶と、それに対峙できず楽観的にふるまう姿が、映画に悲痛な緊張感を与えています。守るべき子には見せられない父のトラウマと、その重さを理解したいと思う娘の気持ち。衝突の先にある"強い親子"の絆に胸を打たれます。
木下優子 [kino cinéma天神] 副支配人
父親に振り回されながらも、なんとかイライラを落ち着かせようとしているルーシーの姿はまさに両親の相手をしている時の私そのものでした(笑)ホロコーストという一見重そうなテーマですが、最後は心がじんわりと温かくなりました。
M・K [kino cinéma神戸国際]
父と娘…娘と父。親子ではあるけれど一番の他人でもある二人。一番近くて遠い存在だからこそ分かりあいたいのにわかりあえない。ロードムービー特有のユーモアな展開と同時にハッとさせられるお互いの心の傷。名女優のレナ・ダナムの演技は必見です。
A [kino cinéma立川髙島屋S.C.館] スタッフ
まだどこかに戦争の気配が残るポーランドをちょっと不器用な父娘があーだこーだ言い合いながら旅する様子に、いつのまにか自分も参加しているようでした。観終わるころには、自分も家族とゆっくり話したい気持ちになるような、そんなあたたかい映画です。
田嶋高志 [kino cinéma] 興行部
もしも山田洋次監督がポーランドに生まれていたら、きっとこんな映画を撮っていたんだろうな。父の過去、娘の抱える現在、家族の未来、そして戦争の遺した暗い気持ち。ちょっと笑えるけど、最後は家族の在り方を考えさせてくれる、まさに宝物のような映画でした。
青木玲依 [kino cinéma横浜みなとみらい]
父と娘の噛み合わない会話に思わず笑いながら、その裏にある言えない痛みがじわりと迫ってくる。旅を通して、二人が自分の中の傷と向き合い、少しずつ歩み寄っていく姿がとても人間的で愛おしい。ホロコーストを“過去の出来事”ではなく、今を生きる者の物語として描いた点も深く心に残った。
今野亮一 [サツゲキ]総支配人
ホロコーストやアウシュヴィッツと聞くと、誰しもが頭にイメージするものがあるはず。ただ本作はその直接的な表現は無い。あるのは、そこに残ったもの。建物や食器、人の心、匂い…。いままで、生存者やその家族のことを、どれだけ深く考えたことがあっただろうか。決して忘れてはならないと、「父と娘」の旅から教わった気がする。
オリ太郎 [伏見ミリオン座]
祖国のはずが祖国ではなくなる悲しみをユーモアを交えて描いた傑作。寒々しいポーランドで嚙み合わない娘と父が絆を少しずつ深めていく道中、家族が失ったものを取り戻していく。ホロコーストを生き残った父は人生を謳歌している一方で、娘はどこか周囲と馴染めない。そんなちぐはぐな二人がとても可笑しく愛おしい。
K.N [角川シネマ有楽町]
ベルリンの壁が崩壊したあとソビエト連邦が解体され東西の分断が終わり世界は大きく変わり始める1991年アウシュビッツの経験と家族のルーツに思いを寄せる父と娘の旅だが悲惨なつらいことばかりではなく人生を前向きにとらえた生き方に観終わったあと救われる思いがした
田上真里 [長野相生座・ロキシー] 支配人
本作は、心の空いた部分にそっと触れる映画です。ポーランドの景色やアウシュヴィッツの風景は、スクリーンで観てこそ深く胸に残ります。旅の途中で明かされる父の不器用な想いに、ラストは静かに涙がこぼれました。私はこの映画を、見返したくなるくらい好きです。